北海道PVGSは「地域活性化のプロデュース」を行う会社です

株式会社
北海道 PVGS
アーカイブ
archive
RSU (譲渡制限付き株式ユニット)のデメリットは?⇒2つ、あります。
RSU
(譲渡制限付き株式ユニット)の
メリットについてはわかりましたが
デメリットはないのですか?

下記を読んでくださった方から
https://bit.ly/3YuAy8w
ご質問をいただいたので
お答えしますと
RSUを付与された
役職員のデメリットとしては
以下の2つが挙げられます。
1)議決権と
配当受領権が発生しない
RSUは
その権利が確定したあとに
株式を付与する仕組みのため
付与された当初は
株主総会での議決権や
配当金の受領をする権利は
残念ながら発生しません。
ちなみに
下記で紹介したRSは
https://bit.ly/3Ks5ccT
権利確定前でも
議決権と配当受領権が
発生します。
2)権利確定時と売却時に
確定申告及び納税が必須
RSUは
権利が確定した年度と
株式を売却した年度に
確定申告及び納税の義務が生じます。

具体的に言うと、
権利が確定した年度には
株式を売却しなくても
保有している株式の時価が
給与所得課税の対象になります。
また、権利確定後に売却したあとは、
RSUの権利が
確定した日の株価から
売却時の株価を差し引いた
キャピタルゲインに対して、
株式の譲渡益課税(約20%)が
発生します。
以前も申し上げましたが
どの制度にも必ず
一長一短がありますので
事前によくよく
検討してくださいませ。
=====================
↓ビジネスに役立つ気づきを無料配信!
メルマガ「ご縁ゴト」お申し込みは下記より↓
https://bit.ly/3o1Odl1
生産性の向上に全く役に立たないロボットが、人間の生産性を向上する!?
今どきの小学生が欲しがる
オモチャがさっぱりわからない
オジサン(私)ですがw
クライアントさんの
オフィスで見た
LOVOT(らぼっと)も
よくわからなかった。。。
LOVOTは
ひとことで言えば
何の役にも立たないロボット(爆)
が、
クライアントの皆さんは
「かわいいでしょう。」
「いやされるー。」
とおっしゃり
正直、私は戸惑った、、、
そんな私に
よかったらこれをどうそと
おススメされて読んだのが
『温かいテクノロジー』↓
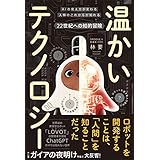 |
![]()
著者は
LOVOTの開発者である林要さん。
LOVOTを開発することは
人間を知ることだった。
と帯にあったとおり
人間とは何か?
愛とは何か?
について、科学者である
著者ならではの視点で
徹底的に考察しており
その見解は時に哲学的
時に壮大さを感じさせ
えもいわれぬ気持ちになった。
本書の中で
特に印象に残った部分を
引用(一部加筆)して紹介すると、
===ここから===
それまで
「ロボットが人のためになにかする」
ことが価値だと考えていた
ぼく(著者)にとって、
「人がロボットを助ける」ことで
助けた人がうれしくなるというのは、
新たな発見でした。
「手を温かくしてほしい」
高齢者福祉施設で言われた一言。
LOVOTは生産的なことはしませんが、
そうして癒された人の
生産性は上がっていきます。
===ここまで===
ロボットは
人を助ける機能がある
生産性を向上するためにあるのが
当たり前だと考えていた
私にとっては衝撃的でした。
そして、著者の
「そもそも」を問う着眼点に
目から鱗の思いを抱きました。
『温かいテクノロジー』↓
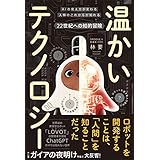 |
![]()
◆目次◆
序章 ぼくらが「メーヴェ」に憧れ、
「巨神兵」に恐怖を覚える理由
1章 LOVOTの誕生
2章 愛とはなにか?
3章 感情、そして生命とはなにか?
4章 人生100年時代、
ロボットは社会をどう変えるのか?
5章 シンギュラリティのあと、
AIは神になるのか?
6章 22世紀セワシくんの時代に、
ドラえもんはなぜ生まれたのか?
7章 ドラえもんの造り方
終章 探索的であれ
『温かいテクノロジー』↓
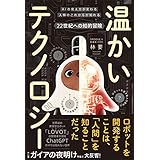 |
![]()
全てのビジネスパーソンに
不可欠なスキルである
「そもそも」を問う力を
養いたい方は、
ぜひ、読んでみてください。
=====================
↓ビジネスに役立つ気づきを無料配信!
メルマガ「ご縁ゴト」お申し込みは下記より↓
https://bit.ly/3o1Odl1
考えが「浅い」、視野が「狭い」、発想が「平凡」がなくなるメソッド
「マーケティングと
一口に言うけれど
人によって定義も違うし
正直言って何が正解なのか
よくわかりません。。。」
きのうも含め
今週も何度か
このようなコメントを
お客様からお聞きしました。
垰本泰隆も
上記のコメントには
全くもって同感です。
が、そもそも
ビジネスに絶対的な
正解がないのと一緒で
マーケティングにも
絶対的な正解なんて
ないんじゃないかと
個人的には思います。
なので、
その時々のトレンドなどを
踏まえながら学び続けて
その学んだことを
とにかく実践してみる。
というわけで
最近読み終えた本の中では
『マーケターのように考える』↓
 |
![]() が、学びと実践のきっかけに
が、学びと実践のきっかけに
最適かなと思います。
私的にはかなり
珍しいケースですが
著者である山本大平さんの本は
ベストセラーとなった
トヨタの会議は30分にはじまり
本書を含めて三冊、読破しました。
なぜかというと
著者の本は
シンプルでわかりやすく
かつ、本質を突いていると
思うからです。
そして本書は
ビジネス書には珍しく
スタートからゴールまで
物語(下記要約参照)で
構成されています。
 |
![]() 食品会社の商品企画部に
食品会社の商品企画部に
配属されて3年目の
主人公の相川タツヤ。
企画が通らない
自分のアイデアが
てんで通用しないと
悩んでいる主人公が
会社で出会った
掃除のオジサンという
不思議キャラとのやり取りを通じて
「どうすれば
お客様のニーズがわかるのか?」
「どうすればお客様が
いいと思う商品を作れるのか?」
という
誰もが知りたい
ビジネスの普遍の課題に取り組み
苦難と失敗を乗り越えて
25年後に
「ギョクロ」という
ヒット商品を生み出すに至った。
この物語を読めば
・考えが「浅い」
・視野が「狭い」
・発想が「平凡」
と、
お客様や上司から
言われた経験のある方や
上記のことで
悩む方の問題解決の
一助になると思います。
『マーケターのように考える』↓
 |
![]() 手軽に読めるけど
手軽に読めるけど
深い示唆を得られる一冊。
ぜひ、読んでみてください。
=====================
↓ビジネスに役立つ気づきを無料配信!
メルマガ「ご縁ゴト」お申し込みは下記より↓
https://bit.ly/3o1Odl1
唯一絶対の正解はない。が、一般的には10年物の利回りを使います。
β(ベータ)と↓
https://bit.ly/3sdd7EW
マーケットリスクプレミアムの↓
https://bit.ly/45b4yJr
説明ではそれぞれ
具体的な数字が
示されていたけど
リスクフリーレートでは↓
https://bit.ly/3Yxpjwk
具体的な数字が
ないですよね。
国債と一口に言っても
短期・中期・長期など
さまざまな期間の
ものがあるけど
株主資本コストの計算では
どの数値を用いれば
よいのですか?
という
じつに鋭い指摘と
ご質問をいただきました。
(Mさん、さすがです♪)
ので、さっそく
お答えしますと
一般的には
10年物の長期国債の
利回りを使います。

10年物の長期国債の
利回りはネットで検索すれば
すぐに出てきますけど
本家本元である
財務省の下記ページを
ここでは紹介します↓
https://bit.ly/3QJDVqA
が、上記で
「一般的」と書いたように
リスクフリーレートに用いる数字は
絶対に10年物の長期国債の
使わなければならないという
決まりはありません。
投資家によっては
投資の意思決定を
おこなう時点での
利回りを使うこともあれば
過去何年分かの
平均値を使うこともある。
また、10年物の
長期国債ではなく
5年物の国債の利回りを
使う方もいたりする。
したがって
「唯一絶対の正解はない」
と考えていただき
自分ならば
利回りが何%ならば
国債に投資しても良いかなあ。
という視点から
数字を選択して
計算してみるのも一手です。
突き放すような
言い方に聞こえるかもしれませんが
さまざまな情報や
アドバイスを踏まえて
最後は自分の頭で考えて
自分で判断して決定する。

投資
(に限らずですが)の鉄則ですよ。
=====================
↓ビジネスに役立つ気づきを無料配信!
メルマガ「ご縁ゴト」お申し込みは下記より↓
https://bit.ly/3o1Odl1
リスクを取った分の利回りが欲しい(ー:引く)国債の利回り=マーケットリスクプレミアム
さて、本日は
株主資本コストの計算式
『株主資本コスト=
リスクフリーレート
+β(ベータ)
×マーケットリスクプレミアム』
のうち、最後の
「マーケットリスクプレミアム」

について説明します。
※ご参考※
リスクフリーレートとは?
https://bit.ly/3Yxpjwk
β(ベータ)とは?
https://bit.ly/3sdd7EW
マーケットリスクプレミアムとは
株式市場全体のリターンと
リスクフリーレートの差を
示すものです。
株式市場全体とは
日本であれば
TOPIX(東証株価指数)
アメリカであれば
S&P500を
一般的には指します。
最近では
NISAを活用した
積み立て投資などで
「インデックスファンド」
なんて名前を
聞いたことがあるかもしれません。
インデックスファンドとは
TOPIXやS&P500などの
株価指数に連動した
投資信託のことです。
たとえば、皆さんが
インデックスファンドに
投資した場合、
そこから得たい利回り
(要求収益率)は
何%くらいですか?
もちろん、
人それぞれだと思いますが
国債に投資した場合の利回り
(=リスクフリーレート)
よりは「高い」ですよね?
以前説明したように
国債は一般的に
リスクゼロと考えますが
インデックスファンドは
個別株式を買うよりも
安全性が高いものの
国債に比べたら
リスクが高いと考えるのが
普通ではないでしょうか?
にもかかわらず
インデックスファンドから
得られる利回りと
国債から得られる利回りが
「同じ」だったら
納得できないですよね。
つまり、
より高いリスクを
取ることに対する報酬を
投資家は求めるわけです。
そしてそれを
「マーケットリスクプレミアム」

と呼ぶわけです。
以上を数字を用いてまとめると
インデックスファンドへの
投資に対する要求収益率を5%、
国債投資への要求収益率
(リスクフリーレート)を0.5%、
と仮定すると、
5%ー0.5%=4.5%
この「4.5%」が
「マーケットリスクプレミアム」
というわけです。
馴染みのない言葉も多く
戸惑いがあると思いますが
CFOを目指す皆さん、
会社の財務を担当する皆さんは
頭に入れておいてくださいね。
=====================
↓ビジネスに役立つ気づきを無料配信!
メルマガ「ご縁ゴト」お申し込みは下記より↓
https://bit.ly/3o1Odl1
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||

