北海道PVGSは「地域活性化のプロデュース」を行う会社です

株式会社
北海道 PVGS
アーカイブ
archive
「できますか?」「もちろんできますよ♪」だって、主人公じゃないですか!
「私たちにもできますか?」
「もちろん、できますよ!」

とある事業会社さんに
スポットコンサルティングを
させていただいた時の会話の一部です。
ご相談内容は
「自社でM&Aをするにあたり
どうすれば相手先と
巡り合うことができますか?」
垰本泰隆も
M&Aの相手先を探すのが
仕事ではあるけれど
今回のご相談は
「自分たちで探したい」
というもの。
さあ、ここからは
同業者の反発や
しかめっ面を覚悟で書くがw
垰本泰隆は
冒頭に書いたとおり
「もちろん、できますよ!」
とコメントし
その具体的な方法などを
アドバイスさせてもらった。
その詳細については
スミマセンm(__)m
さすがにここでは
書けませんので
お知りになりたい方は
下記よりお申し込みを
お待ちしております♪
https://bit.ly/3kG6ylL
なんて宣伝はさておき(汗)
ご相談者からも
「聞いた側が
言えた義理じゃないけど
垰本泰隆のお株を奪うような
話を教えてもOKなんですか?」
なんて言われたが
全然、ノープロブレム♪
だって私たち専門家は
あくまで黒子であって
主人公はM&Aをする
当事者同士じゃないですか。

主客逆転
仲人が自分の都合を
最優先すると
だいたい
ロクな話にならない。。。
これ、M&Aにかぎらず
人間関係も一緒じゃ
ないでしょうかね。
M&Aは業者の
専売特許じゃない。
主人公はあくまで
当事者同士。
賛否両論
甘んじてお受けしますが
垰本泰隆はそれを
確信しているので
今日はこんなことを
書いてみました♪
__________________
↓ビジネスに役立つ気づきを無料配信!
メルマガ「ご縁ゴト」お申し込みは下記より↓
https://bit.ly/3o1Odl1
「反社」に「反市」。どっちも分かりづらくなっているので、くれぐれもご注意を!
「反社」と
「反市」って
どう違うんですか?
IPO準備中の
クライアントさんから
受けた質問。
「反社」とは?
「反社会的勢力」の略。
(参考:Wikipedia)
http://bit.ly/3REyQhF
ざっくり言っちゃえば
暴力団や半グレなどの犯罪集団。
手口が巧妙になり
むかしに比べると
見た目も普通な感じに
なってきてはいるが
いわば誰が見ても
ワルだと気づきやすい輩(爆)

いっぽうの
「反市」とは?
「反市場的勢力」の略。
例としては
総会屋のように
会社の弱みにつけこみ
金をせしめるような輩。
1990年代にくらべると
激減しており、
最近は殆ど聞かないけどね。

いずれにしても
どっちも絶対に
関わっちゃいけない
輩であることは間違いない。

が、繰り返しになるが
どちらも手を変え品を変え
手口などが巧妙になっており
ぱっと見では分かりづらく
なってきている。
ので、以下については
特に気をつけてほしいと思う。
・新規の株主(資金調達・株式移動)
・取引先(縁もゆかりもなく
突然やってきた先)
・役職員の採用
気をつけろって
かんたんに言うけど
どうすればいいのさ?
反社や反市が入ったあとに
排除するのは骨が折れるから
事前調査をして入れないことが不可欠。
調査方法や
その体制の確立などは
ここで全てを書けないので
下記まで連絡いただければ
個別にご相談を承ります。
https://bit.ly/3kG6ylL
あと、ひとつ申し添えると
これって
IPO(新規上場)準備会社に
かぎった話じゃないですよ。
M&Aや事業承継でも
生じる可能性はあるし
それらとも関係ない
会社さんであっても
知らないうちに取引先に
反社や反市が
入っていたりしたら。。。
くれぐれもご注意くださいね。
__________________
↓ビジネスに役立つ気づきを無料配信!
メルマガ「ご縁ゴト」お申し込みは下記より↓
https://bit.ly/3o1Odl1
めずらしい月のほうが、契約しやすいと思います。なぜならば・・・
契約しやすい理由は?
https://bit.ly/3HTqlfr
週末にたくさん
回答メールをいただき
ありがとうございましたm(__)m
なので早速
答え合わせをすると
1月決算のような
めずらしい時期の方が
会計士さんが
監査をする時間を
確保しやすいから。
昔にくらべると
分散する傾向にあるが
それでも日本企業は
3月決算の会社が圧倒的に多い。
ので、だいたい
4月から6月までは
決算監査が集中し
会計士さんは毎年
ゴールデンウイーク返上(._.)
くわえて
上場準備会社の監査は
会社側が監査対応に
不慣れな面があるので
既存の上場会社より
より時間を要することもある。
たとえがアレだけどw
帰省ラッシュのように
短期間にお客さんが集中すると
キャパオーバーで
予約が取れなくなるし

仮に取れたとしても
お値段が・・・お高いですよね(爆)
とはいえ
各社事情はさまざまあり
どうしても決算期を
3月じゃないとダメ!
ということも
あるでしょうが
それがなければ
とくに上場を目指す会社は
決算期を何月にするか?を

よくよく考えてくださいね。
__________________
↓ビジネスに役立つ気づきを無料配信!
メルマガ「ご縁ゴト」お申し込みは下記より↓
https://bit.ly/3o1Odl1
職場で使える人間関係の極意と、仕事力をアップさせる時代を読む力。
みずからの
衝撃的な体験を
淡々と、ときに
客観視したような文体で
描いた『国家の罠』。
 |
![]()
18年前に上記を読んで以来
著者の佐藤優さんの
ファンになった垰本泰隆。
近著
『君たちの生存戦略
人間関係の極意と時代を読む力』
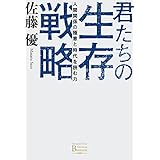 |
![]()
を、読了。
まえがきは著者らしく
ウクライナ問題についての
見立てから始まっているが
昨年著者は
持病が悪化したこともあり
前の世代から
引き継いだバトンを
次の若い世代に
引き継ぎたいと
強く思うようになった。
その中身は
著者の稀有な
人間関係から得た
貴重なノウハウ。
以下の目次を
見ていただければ
ありとあらゆる
ビジネスパーソンが
対象になると
垰本泰隆は考える。
◆目次◆
第一部 明日から職場で使える
人間関係の極意
第一章 人脈づくり
第二章 スキルアップ
第三章 管理職になったら
第二部 仕事力をアップさせる
「時代を読む力」
第一章 時代を読むための洞察力
第二章 歴史の転換点
第三章 社会の危機と未来の破局
第四章 危機を乗り越えるための
考え方
第二部の目次を見ると
なんだか小難しそうだという
印象を抱くかもしれない。
が、
国際情勢だけでなく
いまの世俗にも通じる
幅広い視点を
著者一流の洒脱さで
表現されている。
例えば
第二部の第一章
時代を読むための洞察力
の中にあった
俳優の小芝風花さんの
目的論という箇所は
へえー!
そんな見方ができるのか!
なんて感想を
垰本泰隆はいだいた。
『君たちの生存戦略
人間関係の極意と時代を読む力』
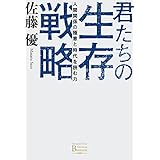 |
![]()
VUCAの時代!
先の読めない時代!
なんて言葉が
飛び交う世の中で
色んな人が色んなことを言っている。
そんな中で
徹底したリアリストかつ
知の巨人である著者の視点や
本質的なアドバイスは
みずからのチカラで
生き残る羅針盤になると思う。
『君たちの生存戦略
人間関係の極意と時代を読む力』
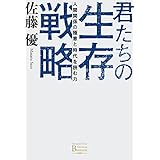 |
![]()
ビジネスパーソンの皆さん
ぜひ、読んでみてください。
__________________
↓ビジネスに役立つ気づきを無料配信!
メルマガ「ご縁ゴト」お申し込みは下記より↓
https://bit.ly/3o1Odl1
退屈と集中。この違いは、なにか?⇒その答えは、意識と無意識にあり?!
同じことでも、人によっては
「あっという間」だったり
「つまんない」だったりする。
んなことは
あたりまえでしょ?
人によって興味や
関心が違うんだから!
ですよねm(__)m
垰本泰隆にとっては
至福のひとときである鉄旅は
いつも
あっという間に終わってしまうw
んが、鉄道に
興味や関心がない人にとっては
退屈で苦痛な移動時間かもしれない。
みたいなw
同じ場面や物事でも
人によって
「退屈」もすれば「集中」もする。
この「退屈と集中」の違いは何か?
脳神経内科医の
田中伸明さんが
『マッキンゼー×
最新脳科学 究極の集中術』↓
 |
![]()
で、わかりやすく
説明しています。
著者は
医師として初めて
マッキンゼー・アンド・カンパニーに
コンサルタントとして採用された
スーパードクター!
と、
絵にかいたような
エリートだったが
マッキンゼー採用後
3ヶ月で自分が
うつ病になってしまった(._.)
そこから回復していく中で
気づいたことを糧に
いまは
べスリクリニック院長として
おもにビジネスパーソンの
メンタルヘルスを診ている。
「集中力」を扱う
本や動画、セミナーは
星の数ほどあるけれど
本書がそれらと
違うなと感じたのが
下記の記述。
「本当に集中できる人は
集中なんて考えていない」
「なぜなら無意識で
目の前の物事に取り組んでいる」
「反対に物事を
意識すればするほど
集中からは遠のく」
「意識と無意識の違いが
集中の差を生み出している」
そして
無意識を操れるようになる技術を
医学的エビデンスにもとづいて
分かりやすく説明しているのが
『マッキンゼー×
最新脳科学 究極の集中術』↓
 |
![]()
垰本泰隆は
多くの示唆を著作から得たが
そのなかでも
「集中力を高めるのではなく
集中を分散されるものを
いかに排除するかが重要」
「解剖生理学にもとづく
集中脳のつくり方
4つのマインドフルネスの実践」
仏教の修業でもある
マインドフルネスは
脳科学的に見て
理にかなったものだと
いうことが
本書を読んで良くわかった(^.^)
そして巻末の
「本書が読者のみなさんの
赤いカプセルになることを
願っています」
(映画、マトリックスより
著者が引用)
に、偽りなしと
垰本泰隆は感じた。
『マッキンゼー×
最新脳科学 究極の集中術』↓
 |
![]()
ビジネスパーソンは
ぜひ、ご一読を♪
__________________
↓ビジネスに役立つ気づきを無料配信!
メルマガ「ご縁ゴト」お申し込みは下記より↓
https://bit.ly/3o1Odl1
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | ||||

